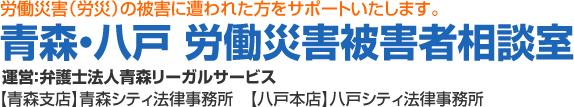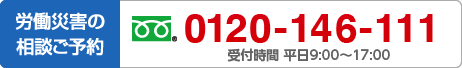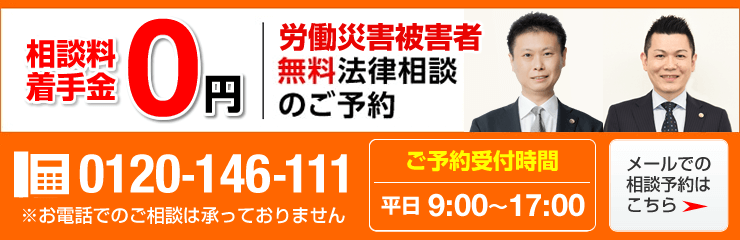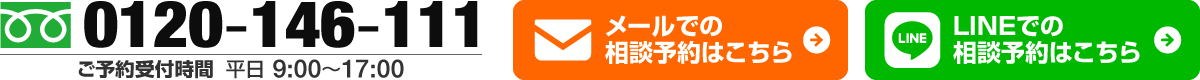労働災害(労災)の被害に遭われた方が労災保険の給付を受けるためには、労災申請の手続が必要となります。
1 労災申請とは?
労働災害(労災)の被害に遭った場合、労災保険から治療費や休業損害などの給付(補償)を受けることができます。
そして、労災保険からの給付を受けるためには、労働基準監督署に労災の申請をする手続が必要です。
この申請の手続のことを労災申請といいます。
2 手続の流れ
労災申請の手続の流れは、以下のとおりです。
(1)労働基準監督署へ労災保険給付の請求書等を提出
労災保険給付の請求書などの必要書類を管轄の労働基準監督署へ提出し、労災の申請を行います。
労災申請は、会社が代行してくれることも多いのですが、中には労災申請に非協力的な会社もあります。
被害者側が主体的に労災申請の手続を行わなければならないこともありますので、労災保険に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
なお、労災申請には時効があり、基本的には時効期間は2年、遺族(補償)給付と障害(補償)給付の時効期間は5年とされています。
傷病(補償)年金給付には時効がありません。
(2)労働基準監督署による事故の調査
労災認定をしてもらうためには、労働基準監督署の審査を通過する必要があります。
傷病が業務と無関係である場合には、労災認定は却下されてしまいます。
労働基準監督署の担当官は、提出された書類を踏まえて、被害者や会社、被害者の家族などの関係者から事情聴取するなど、事故の調査を行います。
(3)労災保険給付の決定
労働基準監督署が事故の調査を経て労災申請の内容に問題がないと判断すれば、労災保険給付の決定を出します。
労災保険給付の決定が出されれば、給付を受領することができます。
3 労災申請をしない場合のデメリット
労災申請の手続がよく分からない、労災申請をして会社に嫌がられたくない、などの理由で労災申請を望まない方もいらっしゃいます。
しかし、労災申請をしなければ、労災保険からの給付を受けることができません。
そして、法律上、労働災害(労災)の場合には、健康保険を使用することはできません。
そのため、労災申請をしなければ、治療費全額を自己負担しなければならないということになります。
労働災害(労災)であることを隠して健康保険使用による治療を受けることは不正であり、刑法により詐欺罪として罰則の適用を受けるおそれがあり、健康保険協会から保険給付額の返金を求められることが考えられます。
たとえ会社から指示されたとしても、このような違法行為に手を染めることがあってはなりません。
4 労働基準監督署が労災認定をしてくれなかった場合の対応
労働基準監督署の審査が通らなければ、労災保険給付を受けることができません。
労働基準監督署が労災申請を却下する決定をし、その決定に納得ができない場合には、決定から3か月以内に、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求という不服申立てを行うことができます。
審査請求をしても決定が覆らない場合には、審査請求を却下する決定から2か月以内に、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。
再審査請求の結果にも不服がある場合には、裁判所に訴訟(裁判)を提起して決着を求めることとなります。
再審査請求を行わずに、訴訟を提起することも可能です。
これらの手続への対応には、専門家である弁護士のサポートを受けられることをお勧めいたします。
5 会社が労災申請に協力してくれない場合の対応
労災申請をするためには、関係書類に事業主の証明のサインを求めるのが通常です。
会社には労災申請に協力する法的な義務があり、事業主の証明のサインを拒否することはできないのが本来です。
しかし、会社が労災隠しに走るケースも散見され、事業主の証明のサインを取り付けられないこともあります。
このような場合には、会社が証明のサインをしてくれないことを労働基準監督署に対して説明した上で、会社の証明がない状態で労災申請を行うことが可能です。
労災申請についてお困りのことがありましたら、お早めに弁護士にご相談いただければと存じます。
労働災害に関する基礎知識についてはこちらもご覧下さい
●労働災害に関する基礎知識
●労働災害とは
●労災保険の申請手続
●労災申請の手続の流れ
●労働災害の被害に遭った時にかかるべき医療機関と制度の仕組み
●労働災害と後遺障害等級
●後遺障害が残った場合の補償について
●後遺障害等級を適正化するポイント
●労災保険の不支給決定に対する不服申立ての手続
●労働災害と損害賠償(労災保険の給付以外に受けられる補償)
●労働者から見た企業の安全配慮義務違反について弁護士が解説
●入院・通院時の損害賠償
●労働災害における慰謝料の請求
●休業中の補償について
●労災における休業補償とは?受け取る条件や期間について弁護士が解説
●損害賠償金の計算方法
●過失相殺について
●仕事中の怪我による労災申請・損害賠償請求について
●労働災害における第三者行為災害とは?事例や対応について