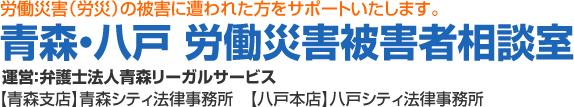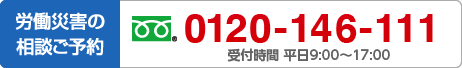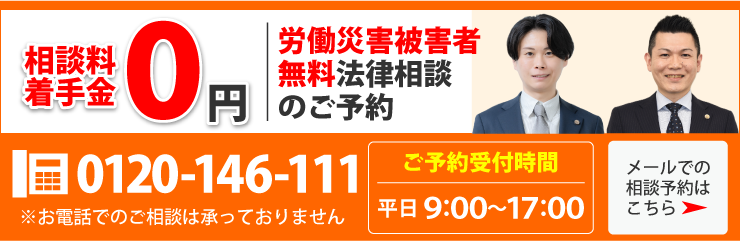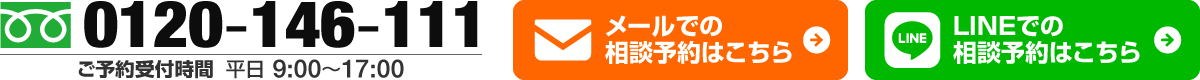1 休業補償とは?

労災における休業補償とは、労働者が業務上発生した怪我や病気によって仕事ができなくなった場合に、国から支給される給付のことを指します。
休業補償は、会社側の都合で従業員を休業せざるを得なくなった場合に支払われる休業手当とは異なります。
休業補償を申請すると、給付基礎日額の60%に相当する休業補償給付と、給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金の給付を受けることができます。
このうち、休業特別支給金については、使用者に対する損害賠償を請求するにあたって、損益相殺の対象にはなりません。
2 休業補償を受け取る条件
休業補償を受け取るためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
(1)業務災害であること
まず、業務災害というためには、災害が発生した場面が、事業者の支配下・管理下にある状態でなくてはなりません。
これは、業務に従事していない休憩中や出張など社外に外出していた際の災害も含まれます。
逆に、故意による災害や天変地異による災害は業務災害に当たらないものと考えられています。
なお、当然ですが、業務災害というためには、業務によって怪我や病気になったという因果関係がなくてはなりません。
(2)療養のため労務の提供ができないこと
これも当たり前ですが、仕事をすることができない場合でなければ、休業補償を受け取ることができません。
もっとも、後述するように、休業補償は休業初日から3日目までは待機期間とされており、この間は休業補償を受け取ることができないため、実際には4日間以上仕事をすることができない場合でないと受け取ることができません。
また、通院などにより、一部の時間しか労働できない場合(一部休業)であっても、給付基礎日額から一部休業によって支払われた賃金の差額の60%が休業補償として給付されます(この場合、休業特別支給金の20%も支払われます)。
ただし、一部休業によって支払われた賃金が、給付基礎日額の60%を超えている場合には、休業特別支給金も含め、休業補償は支払われません。
(3)休業期間に賃金を受け取っていないこと
休業している場合に賃金を受け取っていれば、休業補償を受けることができません。
なお、賃金を全く受け取っていない場合だけでなく、全部休業もしくは一部休業であったとしても、使用者から手当として受け取った金額が給付基礎日額の60%を下回っている場合には「賃金を受け取っていない」ものと扱われます。
3 休業補償を受け取れる期間
休業補償を受け取ることができるのは、前述のとおり、休業の4日目からとなります。
休業初日から3日目までは待機期間となるため、この期間は会社から休業手当が支払われることとなります。
休業補償は、原則として、上記の(1)から(3)を満たす限り、支給されることになります。
したがって、一般に、休業補償の支給が打ち止めとなるのは、治ゆした場合となります(なお、労災保険における治ゆとは、完治した場合に加え、症状固定、つまり、医学的に見て、症状が安定しこれ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態に至った場合も含む概念です)。
ただし、例外として、療養開始から1年6か月が経過した時点で、治ゆに至っておらず、傷病等級表の1級から3級に該当する程度の障害が残っている場合には、傷病補償年金に移行することになるため、休業補償の給付は打ち止めとなります。
逆に、療養開始から1年6か月が経過した時点で、治ゆに至っていなかったとしても、その怪我や病気が傷病等級表の1級から3級に該当しない場合には、原則どおり、「治ゆ」に至るまで休業補償は支給されます。
4 休業補償の注意点
休業補償が支給されるためには、労働基準監督署長に対し決まった書式の請求書類を提出し、労災認定される必要があります。
もっとも、実際には、労災が発生した時点で会社側で労災の報告をする際に、併せて休業補償給付の申請手続きを行うことが多いでしょう(なお、会社の義務として、「休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。」とされています)。
ただし、申請したら直ちに支給されるわけではなく、支給されるまでに1か月程度の時間を要することが一般的です。
特に、初回の支給に関しては、事案によっては、業務との関連性を調査するのに通常よりも時間がかかる場合があります(2回目以降は調査が行われないため、比較的スムーズに支給されます)。
なお、休業補償の申請にあたっては、例えば1月1日から1月20日までの分を申請するといった形で、休業補償を受ける期間を申請の都度、特定する必要があります。
休業補償の支給は、「毎月○日に支給」といった決まりはなく、休業補償は2年間申請しなければ時効が成立してしまうため、こまめに申請をするのがよいでしょう。
5 休業補償の受給額の計算
前述したとおり、休業補償の申請により、給付基礎日額の60%に相当する休業補償給付と、給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金の給付を受けることができます。
ここでいう給付基礎日額というのは、原則として、労働基準法上の平均賃金を指します。
つまり、労災事故の発生日の直前の賃金締切日から直近3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った金額が、給付基礎日額となります(なお、怪我ではなく病気の場合は、労災事故の発生日ではなく、その病気の診断日の直近3か月間となります)。
そのため、休日も含めた日数で計算されます。
なお、直近3か月間に支払われた賃金には残業代は含まれますが、臨時で支払われた賃金や賞与は含まれません。
6 休業補償の申請に必要なもの
休業補償の給付を受けるためには、前述のとおり、労働基準監督署長に対して休業補償の申請をしなければなりません。
その際には、「休業補償給付支給請求書」という決まった書式を提出することになります(この書式は厚生労働省のホームページからダウンロードすることが可能です)。
なお、書式の作成にあたっては、会社に「事業主証明」の欄を、医師から労働することができないことの証明のために「診療担当者の証明」の欄をそれぞれ記入してもらう必要があります。
7 労災に関するお悩みは当事務所にご相談ください
労災に遭われた場合、いつまで怪我や病気の治療が続くのかということはもちろん、仕事ができない間の生活費についても不安になると思います。
特に、一家の大黒柱として家族を支えている方が労災に遭われた場合には、家族の生活もかかってくることになります。
その間の生活をしていくためには、休業補償の給付は不可欠となります。
多くの場合は、会社側において代行してくれますが、会社がまともに手続きを行ってくれなかったり、労災の関係で会社と不仲になってしまったりと、会社に不信感を抱き、連絡を取りたくない場合もあると思います。
このような場合には、弁護士が被害者と会社の間に入って、労災申請についての手続きをサポートすることができます。
当事務所では、労災申請からその後の会社に対する損害賠償請求までの一連の手続きをワンストップでお任せいただけます。
休業補償に限らず、労災についてお悩みがある方は、一度、当事務所にご相談いただければと存じます。
労働災害に関する基礎知識についてはこちらもご覧下さい
●労働災害に関する基礎知識
●労働災害とは
●どこまでが通勤災害?弁護士が回答
●労災保険の申請手続
●労災申請の手続の流れ
●労働災害の被害に遭った時にかかるべき医療機関と制度の仕組み
●労働災害と後遺障害等級
●後遺障害が残った場合の補償について
●後遺障害等級を適正化するポイント
●労災保険の不支給決定に対する不服申立ての手続
●労働災害と損害賠償(労災保険の給付以外に受けられる補償)
●労働者から見た企業の安全配慮義務違反について弁護士が解説
●入院・通院時の損害賠償
●労働災害における慰謝料の請求
●休業中の補償について
●労災における休業補償とは?受け取る条件や期間について弁護士が解説
●損害賠償金の計算方法
●過失相殺について
●仕事中の怪我による労災申請・損害賠償請求について
●労働災害における第三者行為災害とは?事例や対応について