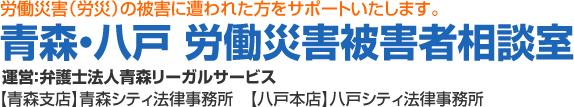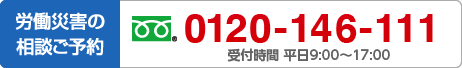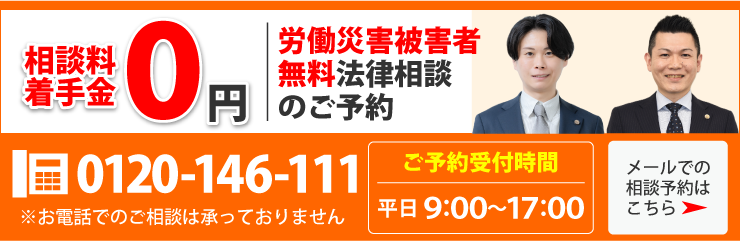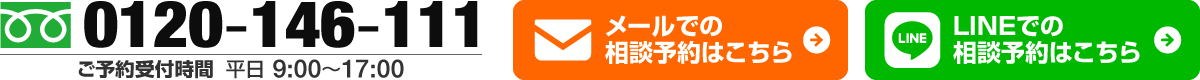1 熱中症の危険性
(1)全国での熱中症による死者数の増加

近年、熱中症による死亡者数は増加傾向にあります。
厚生労働省の発表によると、2020年から2024年の平均は、その20年前である2000年から2004年の5倍近くに達しており、2024年は死者数が2033人に達しています。
このうち、職場における熱中症による死者数は、2018年以降は毎年20人を超えるようになっており、2022年以降は毎年30人以上に達しています。
また、死傷者数についても近年毎年右肩上がりになっています。
これらの原因のほとんどは、初期症状の放置・対応の遅れによるものとされています。
(2)2025年の企業の熱中症対策が義務化
このような背景を踏まえ、2025年6月から、事業者に対し、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う場合には、あらかじめ熱中症対策をしなければならないという義務付けがされることとなりました。
ここで言う「熱中症を生ずるおそれのある作業」というのは、暑さ指数(WBGT)※28度以上または気温31度以上の環境下で、1時間以上連続、もしくは1日4時間を超えて実施が見込まれる作業を指します。
※暑さ指数(WBGT)についての詳細は、厚生労働省の暑さ指数について|職場における熱中症予防情報のページを参照。
この「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う場合には、企業は、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が義務付けられることになりました。
具体的には、
①「熱中症の自覚症状がある作業員」や「熱中症のおそれがある作業員を見つけた者」がその旨を報告するための体制を事業所ごとにあらかじめ定め、関係作業員へ周知すること。
②「作業からの離脱」、「身体の冷却」、「必要に応じて医師の診察や処置を受けさせること」、「事業所における緊急連絡網、緊急搬送先及び所在地等」など熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業所ごとにあらかじめ定め、関係作業員に対して周知すること。
という内容となります。
そして、事業所がこれらの対策を怠った場合には、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が課されることになります。
2 熱中症リスクの高い業種
年によっても異なりますが、熱中症による業種別死傷者数が多い業種は、建設業及び製造業であり、これら2業種のみで全体の約40%を占めます。
これに次いで、運送業、警備業、商業となっており、これら5業種で全体の約75%を占めます。
これらの業種は、当然、個々の具体的な作業内容や事業所によって異なりますが、他の業種に比べ、やはり高温多湿な環境下での作業や休憩・水分補給がしづらい環境での作業が比較的多いことに起因していると考えられます。
3 熱中症が労災となるケース(熱中症の労災認定基準)
熱中症となった場合、それが労災として認定されるためには、①業務遂行性、②業務起因性、の両方を充たしている必要があります。
(1)業務遂行性
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づき、事業主の支配・管理下で業務に従事していることを指します。
業務遂行性が認められる範囲は広く、出張や営業の外回りなどといった場合でも認められるため、空間で区別されるわけではありません。
逆に、休憩中であっても、会社や作業現場にいるといった場合でも業務遂行性が認められる場合があります(ただし、業務起因性が認められるかは別問題です)。
そのため、熱中症に則して考えると、外出先で積極的に私的行為を行い、そこで熱中症になったなど特段の事情がない限りは、業務遂行性が認められるでしょう。
(2)業務起因性
業務起因性とは、発生した災害が業務に内在する危険な要因が原因であることを指します。
業務起因性は、業務遂行性が認められる場合には、業務中の私的行為やいたずらなど業務上と認めがたい事情とは言えない限り、認められることになります。
ただし、休憩時間や終業時間後の時間帯の行為は、私的行為が原因で災害が発生したとして、業務起因性が認められない場合があります。
熱中症は、高温多湿な環境、水分補給の不足、連続作業による体調管理の不徹底などに起因するものと考えられることから、比較的、業務起因性の要件を充たしやすい傷病といえるでしょう。
4 熱中症による労災申請の流れ
労災に遭った場合には、被害者が所属する事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に労災申請することで、療養(補償)給付、休業(補償)給付等を受けることができます(これらをまとめて「労災保険給付」と言います。)。
実際には、多くの場合、企業において被害者の代わりに労災申請を代行してくれるため、それで問題ありません。
もっとも、治療が長期に及んだ場合などには、企業が被害者の症状を分かりかねることから、障害(補償)給付や介護(補償)給付などといった、比較的労災発生から時間を経過してからでないと申請できない給付については、被害者が自身で行うのが確実でしょう。
5 熱中症による企業への損害賠償請求について
以上のように、労災に遭った場合には、労災保険給付により、ある程度の補償を受けることができるのですが、この補償の範囲は、被害者への迅速な救済を目的とするものであり、損害のすべてを補償されるわけではありません。
特に、慰謝料は全く補償されません(被害者が死亡した場合には、被害者の立場によっては、慰謝料の金額が2000万円を超えることは珍しくありません)。
その他、死亡したり後遺障害が残ったりした場合であっても、労災保険給付からは逸失利益は一部しか補償されません。
したがって、このような補償を受ける場合には、企業に対して損害賠償請求を行うことを検討することになります。
もちろん、どのような場合であっても会社に対して損害賠償請求を行うことができるわけではなく、会社に安全配慮義務違反がある場合に限られます。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するよう配慮する企業の義務のことを言います。
そして、企業は労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合には、安全配慮義務違反が認められます。
したがって、2025年6月以降の熱中症対策義務化により、これまで以上に熱中症発生時の安全配慮義務違反の判断基準が明確になりました。
そのため、具体的には、企業には
・作業環境を整備していたか(暑さ指数(WBGT)を低減していたか、休憩場所を設置していたかなど)
・作業環境を管理していたか(水分・塩分の摂取、通気性のよい服装を着用させていたかなど)
・健康管理をしていたか(定期的な健康診断の実施、身体の状況や体調管理をしていたかなど)
・衛生教育をしていたか(熱中症の症状や予防方法、救急措置を教育していたかなど)
といった事情が問われることになります。
6 もし熱中症になってしまった場合は
熱中症になった場合には、まずは作業を中断し、涼しい場所で休息をとる必要があります。
もちろん、速やかに上司や同僚に報告し、医師の診断を受ける必要があります。
そして、労災申請や企業への損害賠償請求を行うために、できるだけ熱中症になった際の状況を記録するようにしましょう。
例えば、どこでどのような作業をしていたのか、当日の暑さ指数(WBGT)はどうだったのか、水分補給や休憩の状況がどうだったのか、などは時間が経つと忘れてしまいます。
また、それにあたっては、同僚の証言を確保するのも有効な方法となります。
7 労災被害を弁護士に相談するメリット
以上のように、労災被害に遭った場合に、企業が労災申請を代行し、その他の損害賠償請求にすんなり応じてくれるのであれば、何も問題はないと思います。
しかし、当然ですが、企業が労災申請を代行してくれない場合には、被害者本人あるいは遺族が申請しないといけません。
その上、原則として、労災申請のためには、労働基準監督署に提出する資料につき、企業から事業主証明欄へ証明印を得ておかなくてはなりませんが、企業がこれに誠実に対応してくれない場合もあります。
また、労災申請を行い、労災保険給付を受けることができたとしても、その他の損害については企業に対して請求していかなければならないところ、これを被害者本人が行うことはかなり負担が大きいところとなります。
それだけでなく、企業は「被害者が勝手に休憩を取らなかっただけ」、「他の人は熱中症になっていないのに、一人だけなったのは自分の体調管理が原因」など、被害者の過失を殊更にあげつらうなど、まともに対応してくれない可能性が極めて高いです。
このような場合には、まずは一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
8 熱中症による労災のお悩みは当事務所にご相談ください
当事務所では、これまで労災に関する相談・依頼を多数対応してきた実績があります。
また、被害に遭われた本人が相談することができない状態にある場合には、ご家族からのご相談も対応しております。
さらに、当事務所では、労災申請から損害賠償請求までワンストップで対応可能です。
その上、このような補償の問題だけでなく、会社とのやり取りについても、当事務所が窓口となるため、被害者の負担は相当楽になると思われます。
熱中症による労災に遭われた方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
部位・症状別の労働災害についてはこちらもご覧下さい
●部位・症状別の労災事故
●仕事中に手の指を骨折した場合に労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に手の指を切断した場合の労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に腕を骨折してしまった場合の労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に腕を切断してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中の熱中症は労災になる?労災申請と会社への損害賠償請求について弁護士が解説