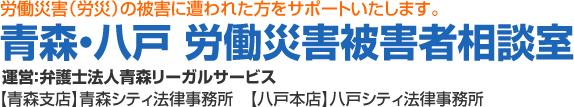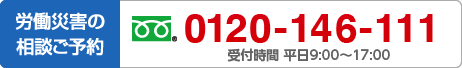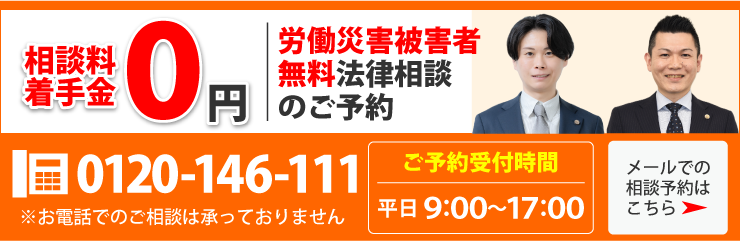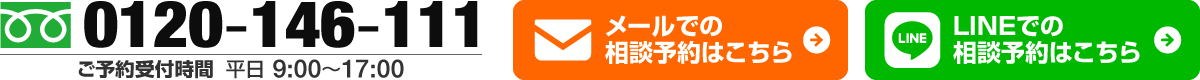1 手指の切断が発生するよくあるケース

仕事中の事故(労働災害)で手指の切断が発生するよくあるケースとしては、次のようなケースがあります。
□工事現場や山林作業で、チェーンソーなどの切断用機械を使用した際に、回転刃に指を巻き込み切断してしまう。
□工場などで、停止していた機械が突然動き出して、回転刃やプレス機に指が挟まり、切断してしまったり、壊死してしまったりする。
□食肉加工機械に肉を投入する際に、指が巻き込まれて切断してしまう。
□重い資材や鉄骨などが指の上に落ち、挟まれて壊死してしまい、結果的に切断に至ってしまう。
など
2 手指の切断による後遺障害について
手指の切断による後遺障害には、欠損障害があります。
手指の後遺障害としては、手指の損傷により指の動きが制限されてしまう機能障害や、痛みや感覚障害などの神経系統の障害もありますが、ここでは欠損障害(手指の切断)に絞って解説いたします。
(1)後遺障害等級表
手指の切断で認定される後遺障害等級は、後遺障害の内容によって、以下のように分類されます。
|
後遺障害等級
|
後遺障害の内容
|
|---|---|
| 第3級の5 | 両手の手指の全部を失ったもの |
| 第6級の7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
| 第7級の6 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
| 第8級の3 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
| 第9級の8 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
| 第11級の6 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
| 第12級の8の2 | 1手の小指を失ったもの |
| 第13級の5 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
| 第14級の6 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
(2)後遺障害の内容の解説
①「手指を失ったもの」とは
「手指を失ったもの」とは、「母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの」とされています。
より具体的には、次の場合が該当します。
□手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
□近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの
分かりやすく言うと、親指の場合は第1関節を切断したとき、それ以外の指(人差し指、中指、薬指、小指)の場合は第2関節を切断したときに該当します。
②「指骨の一部を失ったもの」とは
「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。
③母指延長術について
母指延長術をおこなった場合、術後の母指は切断時に比べて指の長さは延長されますが、その後遺障害は、原則として「1手の母指を失ったもの」(第9級の8)として認定されます。
ただし、術後の母指が、健側母指と比べて明らかに指節間関節を超えている場合には、「1手の母指の用を廃したもの」(第10級の6。機能障害)として認定されます。
④母指機能再健化手術について
他の手指又は足指の移殖により失った母指の機能再健化手術が行われることがあります。
この場合、術後の母指の機能障害と、この手術により失うことになった手又は足の指の欠損障害を同時に生じた障害とみなし、準用または併合の方法により障害等級が認定されます。
⑤手関節(手首)以上を失った場合
手関節(手首)以上を失った場合には、上肢の欠損障害として扱われます。
3 手指の切断事故が労災認定されるまでの流れ
手指の切断事故に遭ったら、もちろんまずは適切な医療機関にて治療を受けることが重要です。
そして、その治療費について、会社が加入している労災保険から出るように、労災認定の手続(労災保険給付の手続)をとる必要があります。
労災認定の申請(労災保険給付の申請書の提出)は会社が行ってくれる場合もありますが、会社が協力的でない場合には、被災者自ら、必要書類をそろえて労基署に提出して申請をします。
申請が受理されて労災と認定されると、治療費である療養(補償)給付や休業(補償)給付などの労災保険給付が受けられます。
そして、治療を受けている中で、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態に達し、主治医から症状固定であると診断された場合には、後遺障害の申請をすることになります。
後遺障害の申請は、症状固定の診断後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、関連資料(レントゲン、CT、MRI画像など)を添えて、労働基準監督署に提出して行います。
後遺障害が認定されれば、等級に応じて後遺障害に対する補償(年金または一時金)が受けられます。
4 手指の切断が労災認定される条件とは?
手指の切断が労災として認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」を満たす必要があります。
「業務遂行性」とは、労働契約に基づき、事業主の支配・管理下で業務に従事している最中に事故が発生したことを指します。
工事現場や山林作業、工場などで働いているときに発生した事故であれば、この業務遂行性は容易に認められるでしょう。
「業務起因性」とは、業務遂行性が認められることを前提に、業務と手指の切断の間に因果関係があることです。
つまり、業務が原因で手指が切断したと認められる必要があります。
業務に関係する作業をしている中で手指の切断が生じた場合には、基本的には、問題なく業務起因性が認められるでしょう。
5 手指の切断によって会社に損害賠償を請求する場合
仕事中の手指の切断事故によって会社に損害賠償を請求するには、まずは労災認定の手続を行います。
そして、認定を受けて労働災害であることを確定した後に、会社が負うべき安全配慮義務違反などの法的責任を立証して、慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求します。
休業損害は労災保険の給付では十分に補償されているわけではないため、会社に対する損害賠償請求の場面で、足りない分を請求することが必要になります。
すなわち、労災保険の給付は必ずしも損害の全額をカバーしない(とくに慰謝料はない)のに対して、会社に対する損害賠償が認められれば、慰謝料をはじめとする労働災害に起因する損害の全額が賠償の対象となります。
損害賠償請求を行うための流れは次の通りとなります。
①事実関係の把握と証拠の収集
事故発生の状況、原因、会社による安全対策、危険防止措置の有無などに関する証拠を収集します。
会社に安全配慮義務違反があったことを証明できる証拠(安全教育の不備、危険防止措置の未実施など)を集めることが重要です。
②会社に対する損害賠償請求の交渉
会社が労働者の安全を守る「安全配慮義務」を怠ったことが原因で事故が発生したことを主張し、会社に賠償責任があることを認めさせます。
他の従業員の落ち度によって手指の切断事故が発生した場合は、会社の「使用者責任」を追及することになります。
6 労働災害でお悩みの方は当事務所にご相談ください
仕事中に手指を切断するという重大な労災事故に遭われた方は、仕事や生活への支障が大きく、後遺障害等級認定や会社への損害賠償請求によって十分な補償を受けることは特に重要でしょう。
そのため、労基署への後遺障害等級認定申請と会社に対する損害賠償請求の両方について、専門家であり包括的な対応が可能な弁護士によるサポートのもとで進めていくことをお勧めいたします。
労働災害でお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
部位・症状別の労働災害についてはこちらもご覧下さい
●部位・症状別の労災事故
●仕事中に手の指を骨折した場合に労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に手の指を切断した場合の労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に腕を骨折してしまった場合の労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に腕を切断してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中に足を骨折してしまった場合の労災認定と損害賠償は?弁護士が解説
●仕事中に足を切断してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中の熱中症は労災になる?労災申請と会社への損害賠償請求について弁護士が解説