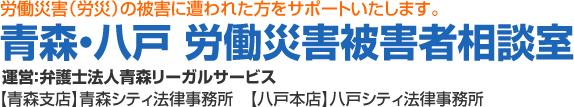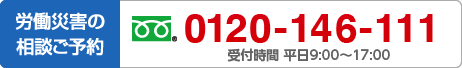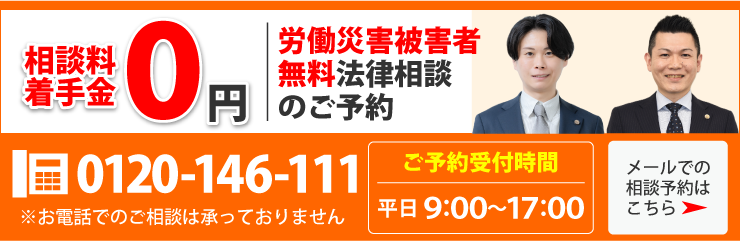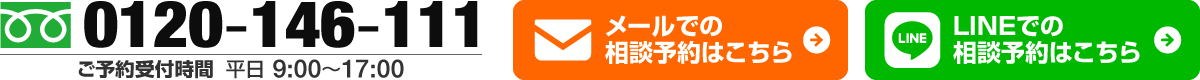1 手指の骨折が発生するよくあるケース

手指の骨折は労災により発生しやすい被害のひとつです。
・荷物の運搬
・機械への巻き込まれ
・転倒
などにより指を挟んだり手をついたりして、手指を骨折する危険があります。
2 手指の骨折による後遺障害について
手指の骨折によって該当する可能性のある後遺障害は次のとおりです。
| 4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 7級7号 | 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの |
| 8級4号 | 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの |
| 9級9号 | 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの |
| 10級6号 | 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの |
| 12級9号 | 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
| 12級12号 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
| 13級4号 | 一手の小指の用を廃したもの |
| 14級7号 | 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
なお、「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
3 手指の骨折による労災保険への申請
業務中に手指を骨折した場合、労災保険への申請を行い、労災認定されることで、補償を受けられる可能性があります。
手指の骨折により支給される可能性があるものとしては、
・療養(補償)給付:治療費
・休業(補償)給付:休業損害の一部
・障害(補償)給付:後遺障害が認められた場合の補償
などです。
申請の手続きは、所定の請求書等の必要書類を用意し、労働基準監督署に提出する方法によって行います。
4 手指の骨折が労災認定される条件
労災保険への申請を行った場合に、実際に労災認定される要件として、①業務遂行性、②業務起因性があります。
①業務遂行性とは、労働者が事業主の支配・管理下にある状況で災害が発生したことを意味します。
事業場内での災害や、出張などで事業所外であっても業務に従事している際の災害であれば業務遂行性が認められることになります。
②業務起因性とは、発生した災害が、業務に伴って発生し得る危険に含まれることを意味します。
作業中の事故や他の従業員のミス、設備不良などによる負傷であれば、当該業務を行っていくうえで発生する危険があるため、業務起因性が認められやすいということになります。
他方で、業務とは関係のないけんかであるとか、自然災害などは業務起因性が認められにくいということになります。
これらの2要件を満たす場合に労災認定がされ、各種給付の対象となります。
5 手指の骨折による会社に対する損害賠償請求
手指の骨折という被害が発生した場合、労災申請のほか、会社に対する損害賠償請求も検討する必要があります。
なぜなら、労災保険では治療費や休業損害・逸失利益の一部は補償されるものの、精神的苦痛に対する慰謝料は補償されないほか、休業損害や逸失利益の残額についても補償されず、十分な補償を受けたとはいえないためです。
これに対し、会社への損害賠償請求が認められれば、労災保険では補償されない損害についても会社から補償を受けることができます。
会社への損害賠償請求については、安全配慮義務違反といった会社の落ち度の有無が問題となります。
会社の落ち度が認められる例としては、機械を使用する作業において安全を図る措置が不十分であった、職場環境が整っていないために転倒事故が発生したといったものが考えられます。
6 労働災害でお悩みの方は当事務所にご相談ください
労働災害については、十分な補償を受けるために、労災保険への申請や会社への損害賠償請求を適切に行っていく必要があります。
手指の骨折という仕事や生活への支障の大きい被害であれば、十分な補償を受けることは特に重要でしょう。
そのため、労働災害に遭われた際には、専門家のサポートのもとで適切な手続きを行っていくことをお勧めいたします。
労働災害でお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。
部位・症状別の労働災害についてはこちらもご覧下さい
●部位・症状別の労災事故
●仕事中に手の指を骨折した場合に労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に手の指を切断した場合の労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に腕を骨折してしまった場合の労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に腕を切断してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中に足を骨折してしまった場合の労災認定と損害賠償は?弁護士が解説
●仕事中に足を切断してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中の熱中症は労災になる?労災申請と会社への損害賠償請求について弁護士が解説