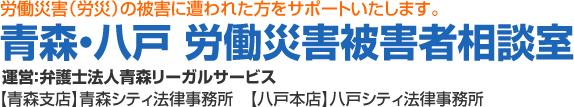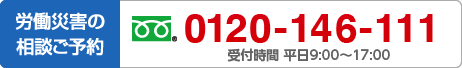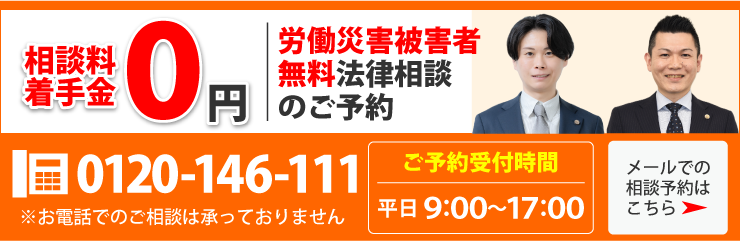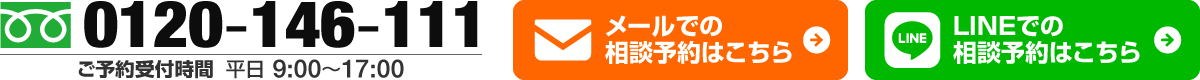1 腕の骨折が発生するよくあるケース

労災事故で腕の骨折が発生するケースは、建設業、製造業、運送業など、さまざまな業種で、転倒・転落、挟まれ・巻き込まれ、落下物との衝突、交通事故など、さまざまな状況で発生します。
建設業における労災事故では、建設現場などで、足場の不安定さや安全帯の不適切な使用により、高所から転落して腕を骨折するケースがあります。
製造業における労災事故では、製造工場などで、プレス機やコンベアなどの産業機械に腕を挟まれたり、巻き込まれたりして骨折するケースがあります。
運送業における労災事故では、車両の運転中に交通事故に巻き込まれたりして腕を骨折するケースがあります。
そのほか、建設現場や倉庫などで、落下してきた資材や重量物と衝突して腕を骨折することがあります。
さらに、濡れた床や段差、滑りやすい場所で転倒した際、とっさに手をついて腕を骨折するケースも見られます。
なお、バイクや自転車での通勤中に、転倒したり交通事故に巻き込まれたりして腕を骨折するケースや、徒歩での通勤中に、急いでいたり路面の状態が悪かったりする際に転倒し、腕を骨折するケースもあります。
さらに、長期間にわたる過重な労働が原因で疲労骨折を起こし、労災事故と認められるケースもあります。
2 腕の骨折による後遺障害について
労災事故における腕の骨折による後遺障害は、機能障害、変形障害、神経障害の3種類あります。
(1)機能障害
腕の骨折による機能障害とは、骨折後に、肩、肘、手首などの関節の可動域が制限されたり、動かなくなったりする状態です。
腕の機能障害については、次の通り、1級から12級までの後遺障害等級があります。
|
等級
|
認定基準
|
|---|---|
| 1級7号 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 5級4号 | 1上肢の用を全廃したもの |
| 6級5号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級9号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
(「これに近い状態」とは、他動では稼働するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいいます。)
③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの以外のもの
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
(2)変形障害
腕の骨折による変形障害とは、元々の形状や機能と異なる形で癒合してしまった状態です。
腕の変形障害については、次の通り、7級、8級、12級の後遺障害等級があります。
|
等級
|
認定基準
|
|---|---|
| 7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、第7級9号の①以外のもの
②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、第7級9号の②以外のもの
③橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
長管骨とは、長い棒状の骨のことであり、上肢では、上腕骨、橈骨、尺骨です。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
a上腕骨に変形を残すもの
b橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの
②上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
③橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
④上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
⑤上腕骨の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨の直径が1/2以下に減少したもの
⑥上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの
(3)神経障害
腕の骨折による神経障害とは、骨折後に痛みやしびれなどの神経症状が残る状態です。
神経障害は、12級と14級があります。
|
等級
|
認定基準
|
|---|---|
| 12級12号 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級は、神経障害の存在が他覚的に証明できるもの、14級は、神経障害の存在が医学的に説明可能なものと言われています。
12級の他覚的に証明できるものとは、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査や、神経学的検査など、客観的に認められる医学的な所見によって、症状の存在が証明できる状態を指します。
14級の医学的に説明可能なものとは、画像所見などの他覚的所見がなくても、事故の状況、治療の経過、症状の一貫性などから、事故に起因するものであると医学的に説明できる状態を指します。
3 腕の骨折事故が労災認定されるまでの流れ
(1)労災認定されるまでの一般的な流れ
腕の骨折が労災認定されるまでの一般的な流れは、労災事故による腕の骨折に対して治療を受け、必要書類を準備して労働基準監督署に提出し、調査・審査を待ちます。
治療を受ける際、労災指定病院で受診すると、窓口での治療費支払いが不要になります。
指定病院以外で受診した場合は、一時的に自己負担した治療費を後で請求する手続が必要となります。
受診した医療機関には、労災事故による怪我であることを必ず伝えます。
それから、補償の種類(療養補償、休業補償など)に応じた請求書(様式)を準備します。
請求書には、通常、事業主(会社)の証明が必要ですが、会社が協力的でない場合でも、被災労働者本人が直接労働基準監督署に提出することができ、その際は事業主の証明がなくても受理してもらえます。
そして、作成した請求書を、事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。
提出された書類に基づき、労働基準監督署が事故の状況や業務との因果関係を調査します。
調査の結果、労災事故と認定されると、労災保険の給付が決定され、給付が開始されます。
(2)後遺障害が残った場合
腕の骨折に対して治療を続けても症状が改善せず「症状固定」となった後も機能障害などが残った場合は、別途、後遺障害の等級認定を申請します。
まず、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、再度、労働基準監督署に障害補償給付の請求を行います。
そして、労働基準監督署が審査し、後遺障害の等級が決定されます。
4 腕の骨折が労災認定される条件とは?
腕の骨折が労災事故として認定されるには、骨折が「業務災害」または「通勤災害」のいずれかに該当し、労災事故と認定される必要があります。
具体的には、仕事中の事故であること(業務遂行性)と、業務に起因して負傷したこと(業務起因性)の両方が認められる必要があります。
また、通勤災害の場合は、自宅から職場への通常の経路での通勤中に起きた事故である必要があります。
業務遂行性とは、労働契約に基づいて事業主の管理下で業務を遂行していた際に発生した事故であることをいいます。
建設現場で足場から転落して骨折した、製造工場で機械に手を挟まれて骨折した、ということであれば、問題なく認められます。
業務起因性とは、業務と負傷の間に因果関係があることで、業務に関連する作業中に起きた骨折は通常認められます。
通勤災害の場合、自宅と会社の間を「通常の経路」で往復している途中で起きた事故であることが必要で、遠回りや寄り道をしていた場合は、原則として認定されません。
冒頭で述べたように、疲労骨折のように、長期間にわたる過重な労働が原因で骨折した場合も労災認定される可能性がありますが、この場合は、仕事と骨折との繋がり(業務起因性)を明確に証明する必要があります。
5 腕の骨折によって会社に損害賠償請求をする場合
腕の骨折によって会社に損害賠償請求をするには、まず労災申請をして労災認定を受け、後遺障害が残った場合にはその後遺障害の等級認定も受け、労災保険から補償を受けることが前提です。
その上で、会社の安全配慮義務違反や注意義務違反(過失)が認められる場合に、労災保険では補填されない慰謝料や逸失利益などを追加で請求できます。
つまり、会社に損害賠償請求をするには、会社の「安全配慮義務違反」や「注意義務違反」を証明する必要があります。
安全配慮義務違反・注意義務違反とは、会社が労働者の安全を確保するために必要な措置を怠ることです。
そして、会社が労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、義務違反が認められます。
例えば、危険な作業場に安全装置を設置していなかったり、労働者に安全教育を施していなかったりした場合などが該当します。
ここで、会社の義務違反を証明するためには、会社が負うべき義務とその違反の有無などを細かく検討する必要があり、法的な専門知識が必要です。
そして、適切な資料を集め、会社との交渉や法的な主張を効果的に行う必要もあります。
6 労働災害でお悩みの方は当事務所にご相談ください
労働災害については、そもそも労災認定の申請を漏れなく行い、後遺障害については適正な等級の認定を受けることや、場合によっては会社に対する損害賠償請求も問題となります。
一般的に、後遺障害の認定申請は、後遺障害の証明のための資料収集を含め困難を伴うこともありますが、弁護士にご依頼いただければ、適正な等級の認定に向けたサポートが可能です。
さらに、会社に損害賠償請求する段階では、会社に過失が認められるかどうかは、労災発生時の状況や会社の指導体制などの多くの要素を考慮して判断する必要がありますので、一般の方にとっては難しいことが現実です。
法的な専門知識が必要ですし、適切な資料を集め、会社との交渉や法的な主張を効果的に行う必要がありますので、専門家である弁護士のサポートが必要といえます。
そのため、労働災害でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
部位・症状別の労働災害についてはこちらもご覧下さい
●部位・症状別の労災事故
●仕事中に手の指を骨折した場合に労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に手の指を切断した場合の労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に腕を骨折してしまった場合の労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に腕を切断してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中に足を骨折してしまった場合の労災認定と損害賠償は?弁護士が解説
●仕事中に足を切断してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中の熱中症は労災になる?労災申請と会社への損害賠償請求について弁護士が解説